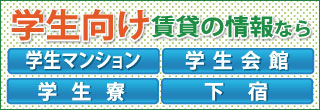【PR】カリスマ講師の授業動画数、なんと1000以上!今なら1カ月お試し無料。

推薦入試 - 大学受験
■ 受験生の皆さんへ
主に大学や高校が学生を募集する際に、出身校からの推薦を受けた学生を選抜して入学させることを推薦入試と呼びます。選抜の基準は、学業やスポーツ、芸術分野など大学・高校が要求する特定分野の成績、調査書等で判断されます。近年は自己推薦、社会人推薦など出身校の枠や現役・浪人を問わないなど推薦入学の形態も変化しつつあります。従来は私立学校で多く行われており国公立校での実施例のほとんどは大学のものでしたが、近年では公立高校などでも増加しています。
大学受験のシステムを知ろう!年に一度の合格チャンスを逃さない為に受験システムを知る
大学受験の
システムを知ることは、決して無駄では有りません。むしろ、大学の受験システムを知らないと慌ててしまう場面があります。色んな入試が有りますので、おおまかにご紹介致します。
大学受験 - 推薦入試って?
推薦入試には、学校側と受験者側にそれぞれいくつかのメリットがあります。学校側にとってのメリットは、一般入試の前に個性的な学生を確保できることや、学校の教育理念にあった学生を早期に確保できることです。受験者側にとってのメリットは、早期に合格を確保できること、一般入試に比べて面接重視の試験なので、人間性をアピールできること、学力ばかりでなく学校生活(生徒会や部活動など)も評価対象になるため、普段の真面目な生活態度や努力の積み重ねが評価してもらえることなどです。
予備校~大学受験 - 推薦入試の種類と対策
(1)指定校制……特定の学校を指定するもの
(2)地域指定制……特定の地域の在住者や学校の卒業者(および見込者)を指定するもの
(3)公募制……上記以外のもの
(1)~(3)以外のものとして「社会人推薦制度」、労災系の「病院長推薦制度」や、公募制+指定校制の「併用制」などもあります。都道府県市立の公立看護医療系学校はその設立意図からほとんどが「地域指定制」か「指定校制」をとっています。
【受験の種類を選ぶとき、教科や科目で自分に合った入試の絞込みをする方法もあります。】
得意科目で受験する
誰にでも得意な科目や不得意な科目はあるものです。自分が得意とする科目のみで受験する方法や、不得意科目を省いた学科を組み合わせて受験する方法もありますので、あなたの個性や希望を活かせる受験方法を考えましょう。
自己PRの書類とは
AO入試を行なう多くの学校で必要なのが、自己PRをする書類です。これを書くためには、まず高校の想い出の中で、やり遂げたことや印象深い出来事などを全部書き出し、次に請求した資料やパンフレットを何度もチェックし学校の特色を理解しましょう。自己PRポイントをまとめ、自分でしかできないこと、自分だからできることなど、具体的な体験を織り交ぜながら、まとめて行きましょう。最後に何度も読み返したり、学校の先生や親等の第三者にアドバイスを貰いながら、自分が伝えたいことがしっかり伝わるように書き換えていくことが大事です。
面接試験
推薦入試やAO入試の受験科目の中に必ずといっていいほど含まれているのが面接試験です。面接では上手に話すことができるというよりも、貴方がどんな目的や意識を持っているかを判断します。ですから、どんなことに興味を持ち、どんな努力をしたか、志望動機、自己PR、入学後学びたいテーマなどが選考項目に入ります。自分のことなので、人前で自信を持って話すことができるように練習をしましょう。
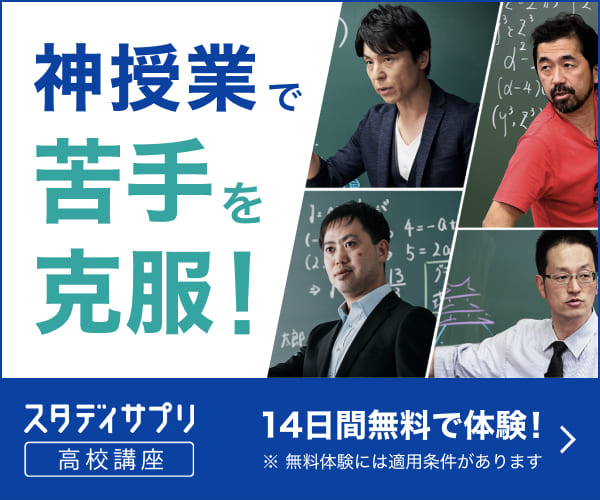

予備校~大学受験 - 推薦入試の応募基準
推薦の応募基準では、「学校での成績」、「卒業年次(現役か浪人か)」がポイントとなってきます。(詳細は各大学により多少異なります)
学校での成績
成績基準として「評定平均値の平均」、「評定平均値の指定科目の総合(国数理3科目の加算など)」、「学習成績概評(A~E)」で定めています。
成績はおよそ高校3年1学期まで(2学期までもとめる学校もあります)が対象となります。
大学では、4.0以上の学校が多いですが、特に医療系では、3.5以上の学校も増えています。短期大学・専門学校では、3.0以上または3.5以上の学校が多くなっています。
現役・浪人の違い
大学・短大の場合、約50%の学校が現役生のみですが、1浪~5浪まで可能とする学校もあります。看護専門学校においては全体の75%以上が現役生のみで、まだまだ、現役生に有利な推薦入学制度といえるでしょう。
大学受験 - 推薦入試の合否選考方法
指定校制の推薦入試では、「書類審査」、「面接」、「小論文(作文)」がほとんどですが、地域指定制・公募制では「学科試験」を加える学校も相当数あります。そのほかに、「適性検査」、「健康診断」を加える学校もあります。公募制は、国公立大と同じく、大学が指定する成績などの応募条件を満たしてさえいれば、どの高校の生徒でも出願できる推薦入試で、多くの大学で実施している形態です。応募条件の中で、他大学との併願を認めているケースもあるのが私立大の公募制の特徴です。そのため、合格すれば入学という制限も少なくなりつつあります。合否判定は通常、書類審査、小論文(または実技など)、面接などにより行われるが、関西地区などでは学力試験を課す大学・学部もあります。
<推薦入試の選抜内容>
(1)…書類審査のみ
(2)…書類審査 + 面接
(3)…書類審査 + 学科試験
(4)…書類審査 + 面接 + 学科試験
(5)…書類審査 + 面接 + 小論文
(6)…書類審査 + 面接 + 実技試験
※小論文は評論文の読解、計算問題が含まれるなど、学科試験に近いものであったり、面接も口頭試問に近いケースが見られます。これは、学力テストの代わりに使おうという意図があるためです。
大学受験 - 推薦入試の募集人数など
私立大推薦入試の募集人員は、定員の50%以内。近年は、出願条件(成績基準や卒業年度)を緩めたり、他大学との併願を認めたりするケースが増えています。募集人数は若干名から定員の50%とさまざまです。指定校制の場合は1校1名(または2名)とはじめから枠が決められていますので、校内での競争となるのはご存知のとおりです。ただし一部ではありますが、指定校推薦で不合格となる場合もありますので油断は禁物です(公表倍率で1.0倍以上の学校はこうした学校です)。 推薦は原則的には専願ですので、見事推薦入試に合格した場合は、必ず入学しなければならないということにも注意しましょう(併願を認めているところもあります)。つまり、合格=入学になるわけですから、受験した学校が本当は第一志望校でないとすると、後に後悔したり、入学してから校風と合わずに退学してしまうことにもなりかねません。こうしたことを考えたうえで、推薦入試を受けるかどうか検討してください。単純に「早く受験から逃れたい」ということだけで決めてしまわないようにすべきです。
各大学の推薦入試資料請求 - 国公私立大学・短大 AO入試・推薦願書を含む資料請求

全国の国公立・私立大学・短大、大学院・ロースクールなどの募集要項(願書)や学校案内がテレメールで請求できます。